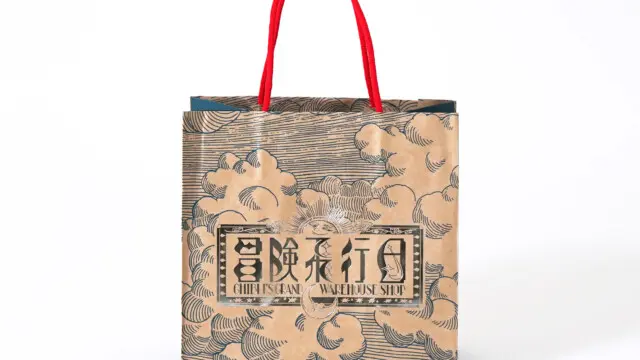ブライダル事業を展開する会社のSDGsに貢献したウェディング用紙袋
2024年12月12日
こんにちは!ベリービーの田上です!
いきなりですが、みなさん「肉」or「魚」どちらがお好きでしょうか?
僕は魚が「超」がつくほど大好きなのですが、中々共感してくれる人が少なく、魚が大好きな人を探しています。笑
この時期になると海鮮類がとても美味しいですよね。毎年12月頃になると何を食べようか必死に悩んでいます。
今年も残すところあと少し!みなさんも美味しいものをたくさん食べましょう!
さて、早速ですが、今日のパッケージをご紹介していきましょう!
目次
ブライダル企業が手がける、上質に輝くロゴが美しいオリジナル紙袋
今回ご紹介するのは、ロゴが上質に輝き、樹や鳥のマークが立体的に浮き出ているこちらのオリジナル紙袋(パッケージ)です!
経営理念が息づくブライダル企業の紙袋
この素敵な紙袋を手がけたのは、2003年に設立されたブライダル事業を展開する企業です。
挙式や披露宴の企画から運営まで幅広く手掛け、旧来の結婚式のあり方に捉われない新しいスタイルを提案しています。
この企業は、「時代が変わっても、「人の力」は変わらない。信頼できるスタッフ、信頼できるチームで顧客の期待を超えていく。」という素晴らしい経営理念を掲げており、社名は「STAFF CREATE」という言葉に由来しているとのことです。
しっとりとした質感が魅力!晒クラフト紙のブライダルショッパー
紙の素材には、しっとりとした質感が特徴の「晒(さらし)クラフト紙」が採用されています。
一般的なクラフト紙と比べると、よりソフトで上品な印象を与えたい場合に効果的です。
ショッパー(紙袋)の大きさはA4サイズで、マチが広めに作られています。
これにより、結婚式の引き出物などを入れる際にも非常に便利ですね!
3つの加工が織りなす高級感:箔押し、エンボス、UV印刷
写真では少し見えにくいかもしれませんが、ショッパーのボディ部分には「太陽と月」「二羽の鳥」「ベールの樹」といったモチーフが、UV印刷とエンボス加工を組み合わせて華麗に描かれています。
このイラストのコンセプトは「愛の輪廻」をテーマにしています。この世に生を受けた二人(月と太陽)が、やがて結ばれて夫婦となり(二羽の鳥)、幸せの花を咲かせる(ベールの樹)という、結婚という美しい節目を表現しているそうです。
まさに挙式や披露宴にぴったり!まるで二人の結婚を一緒に祝ってくれているような、心温まるデザインですね。
ロゴ部分には、高級感あふれるゴールドの箔押し加工が施されています。
箔押しは、熱と圧力を加えて金属光沢のある箔を転写する加工で、デザインに特別感をプラスします。
また、先ほど触れたショッパーのボディ部分のイラストには、UV印刷(紫外線を照射してインクを硬化させる印刷方法)とエンボス加工が用いられています。
通常のUV印刷だけでは難しい立体感を、エンボス加工(紙を型でプレスして凹凸をつける加工)を施すことで表現し、デザインのナチュラルな印象を一層引き上げています。
環境に優しい紙ファイバーハンドルを採用
ハンドルには、紙ファイバー素材を用いたエコな平紐が採用されています。
紙ファイバーは紙を使用しながらも、しなやかで肌触りの良い質感が特徴的です。近年では現代アート作家からも注目されるほど、デザイン性が高く、さらにリサイクル可能なサステナブル素材としても注目されています。
ベリービーでも、紙ファイバーハンドルを取り扱っています。ご興味のある方は、ぜひこちらのページをご覧ください!
SDGsとFSC認証マークで示す企業の環境配慮
底面部分には、FSC認証マークとフォレスト環境認定マークが印刷されています。
FSC認証は、適切に管理された森林から生産された木材を使用していることを示す国際的な認証です。
こちらの会社は、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みにも積極的に力を入れており、人と地球がいつまでも共存していける持続可能な社会の実現を目指しているとのことです。
人と地球が共存できる社会を目指す、サステナブルな紙袋をお探しの方は、ぜひバリューペーパーバッグで詳細をご覧ください。
いかがでしたでしょうか?
今回のブライダル企業のオリジナル紙袋は、結婚式という特別なシーンにふさわしい、上質で美しいデザインでしたね。
さらに、FSC認証紙や紙ファイバーハンドル、そしてSDGsへの積極的な取り組みなど、地球環境への配慮も感じられる、まさに現代に求められるパッケージデザインの好例でした。
これからも様々なパッケージデザインをご紹介していきますので、この記事を読んで面白いなと思っていただけたら、ぜひまた覗きに来てみてください。
オリジナル紙袋やオリジナルパッケージの制作をご検討中でしたら、ぜひベリービーにお気軽にご相談ください!お客様のこだわりを形にするお手伝いをさせていただきます。
それではまた次回の記事で!