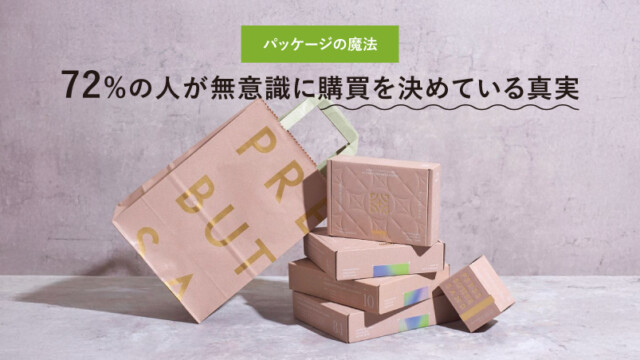記憶に残るブランド作り|エボークトセット理論とオリジナル紙袋の力


(画像元:PR TIMES)
街でふと目に入ったオリジナル紙袋が、なぜかあなたの心をくすぐったことはありませんか。
それは、ただの紙袋ではなく、あなたの記憶の奥にある“ブランドの引き出し”を開ける鍵かもしれません。
USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)の再生などで有名なマーケティングの第一人者・森岡毅氏が提唱する「エボークトセット理論」によると、人は何かを買おうとするとき、最初に思い浮かぶブランドはせいぜい3〜5社ほど。この“想起集合”に入らなければ、そもそも購買の土俵にも上がれません。では、どうすればその短いリストに入れるのか。実は、オリジナル紙袋がその突破口になるのです。
前回記事:マーケター・森岡毅さんの考え方について▼

(画像元:DECORTÉ)
ブランドの価値を伝える「オリジナル紙袋」の5つの力

(画像元:SHIPS)
①感情をブランドに“移す”オリジナル紙袋
心理学では感情転移と呼ばれる現象があります。
高級感のあるオリジナル紙袋を手にすると、その感覚がブランドの価値そのものとして記憶されます。
「この紙袋=このブランドは質が高い」という無意識のラベルが貼られるのです。
②記憶に残る確率はデジタル広告より70%高い
ある研究によれば、オリジナル紙袋を含む印刷物のブランド想起率は、デジタル広告より70%も高いと言います。五感で触れられる物理的なメディアは、脳にとって処理負荷が軽く、記憶に深く刻まれるのです。
③「最後の印象」を握る
買い物の最後に手渡されるオリジナル紙袋は、ブランドとの体験の締めくくり。ピークエンドの法則により、この瞬間の印象が全体の記憶を左右します。美しいオリジナル紙袋は「またここで買いたい」という感情を静かに育てます。
④日常に溶け込む広告塔
オリジナル紙袋は持ち帰った後も家や職場で目に入ります。さらに、他人の視界にも入り、第三者の記憶にまでブランドを忍び込ませる。これはデジタル広告には真似できない、生活密着型の反復露出です。
⑤無言で伝える信頼感
物理的な紙袋には「コストをかけている」感覚が宿ります。
それは「この会社は顧客を大事にしている」という信号として受け取られ、ブランドの信頼度を静かに押し上げます。
オリジナル紙袋は“記憶をデザインする”メディア

ブランドの成長に必要なのは、認知されることより思い出されることです。
紙袋は、そのための最も身近で、そして長く効くツールです。
次に紙袋を作るときは、ただの包装ではなく、「未来の購買を引き寄せる鍵」としてデザインしてみてください。あなたのブランドは、きっともっと多くの人の記憶に残るはずです。
オリジナル紙袋・パッケージについてのお悩み、リブランディングなどをご検討中の方、ブランディングを考慮したパッケージ提案をご希望の方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
東京、大阪にショールームもございます。遠方の方はオンラインでのお打ち合わせも可能です。
ぜひお越しください!
おすすめの記事
-
光を包む箱。クリスマスコフレに宿る「ご褒美心理」
▲BAZAAR なぜ毎年、クリスマスコフレは完売するのでしょうか? 競合が激しいホリデーシーズン、選ばれるブランドと埋もれるブランドの差は「パッケージの演出力」にあります。限定性を感じさせる外装デザイン、開封体験の設計、 […]

-
クリスマスこそ、パッケージが売上を左右する。記憶に残るホリデー戦略とは?
クリスマスシーズン、あなたの店頭は特別な輝きを放っていますか? 日本のクリスマス関連市場規模は約2兆円と推計され、年間で最も購買意欲が高まる時期です。 しかし、2024年のクリスマス平均予算は前年比約3割減の16,329 […]

-
パッケージの魔法:72%の人が無意識に購買を決めている真実
(画像元:PRESS BUTTER SAND) 買い物中、なぜかある商品に手が伸びてしまった経験はありませんか? 「なんとなく素敵だと思って」「紙袋がかわいくて」そんな理由で選んだ商品、実は多いのではないでしょうか。 実 […]